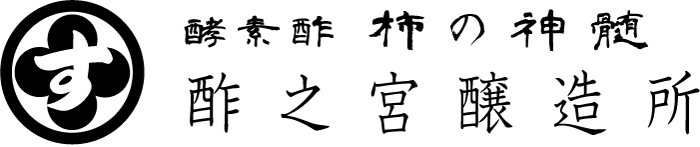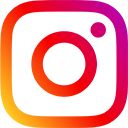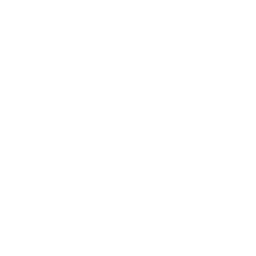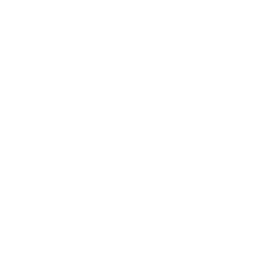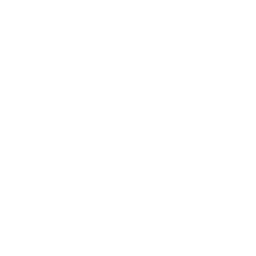工場で培養する微生物には限界がある
先日、よく聴いているラジオ番組に土の研究者である藤井一至さんがゲストでいらっしゃいました。土の歴史や種類について大変興味深いお話をされていたのですが、特に印象的だったのは「落ち葉一枚でも土に還すことは、工場では不可能」ということでした。
落ち葉を腐葉土化するには、1万種以上の微生物が必要だそうです。それぞれの微生物がそれぞれの役割を果たすことで、初めて落ち葉は土へと還ります。
ですが、工場でこれらすべての微生物を培養することはできません。なぜなら、微生物それぞれの生育に必要な条件が異なるため、人間がコントロールするには限界があり、単独で培養したとしても、同じ条件下で置いておくことはできないのです。
この、人間には作り出せない壮大な技術を、自然はたやすく見せてくれます。だからこそ、自然は私たちを飽きさせません。
「柿の神髄」に見る天然発酵の力
さて、「柿の神髄」は、柿の天然酵母菌と天然酢酸菌によって発酵しています。天然の発酵菌の面白さは、その多様性にあります。多種多様な菌が何をするか、全てを把握することはできません。しかし、彼らは自分たちの役割を間違いなく果たしてくれています。そして、そこから生み出される様々な酵素が「柿の神髄」には含まれています。
酵素にはそれぞれ役割が異なります。お客様の声をいただいていると、多種多様な酵素を、皆さまそれぞれの形で体感してくださっているように思います。
目に見えない世界の理
また、以前読んだ「超・進化論」という本に、次のような記述がありました。
「もし、森のやり取りを可視化できたら、森はもっとカラフルかもしれない」
これは、草木や虫、微生物が互いにコミュニケーションを取っていることが分かっている、というお話でした。人間には感知できない周波数や微量な物質によるものなので、目で見たり感じたりすることはできません。もしそれを可視化できたなら、豊かな色彩が森を彩る…とそう想像しただけで、感動して震えるような思いでした。
私たちは、目に見えるものだけで物事を理解しようとしがちです。しかし、空気や音、微生物など、普段から目に見えないものに囲まれて暮らしているのです。
そして、この目に見えないものの「理(ことわり)」によって、世の中は成り立っているのだと、藤井さんのお話を伺っていて、改めて教えられました。
もちろん、工場で培養された酵母を使っても柿は発酵します。しかし、「柿の神髄」と同じにはなりません。その目に見えない違いを、ぜひ感じ取っていただけたら幸いです。
 注ぐ柿の神髄
注ぐ柿の神髄